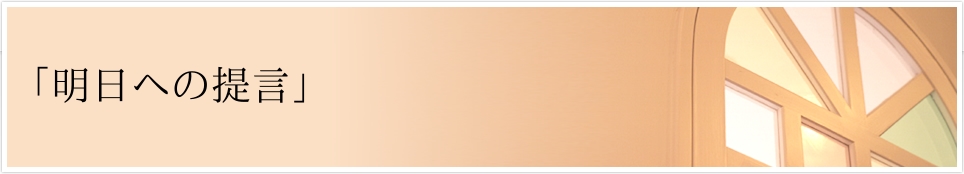齋藤 忠夫(東北大学大学院農学研究科 教授)
私たちの腸管には、沢山の微生物が棲んでいる。研究者によっては、ヒトとこれらの腸内微生物とは「共生」していると表現する場合もある。共生とは、共に足りない部分を補い合って、助け合いながら生きているという意味である。蟻とアリマキ、珊瑚とクマノミなどの共生関係は好例である。
実際に、ブタなどの飼養実験では、腸内に微生物がいない無菌ブタの方が体重増加率は高く、腸内微生物がブタの腸管内で栄養成分を横取りしていることは事実である。この場合には、腸内細菌は腸管に寄生する「悪者」に感じる。一方では、私たちが少しの食中毒菌を食べても、健康な方であれば食中毒は発症はせず大事には至らない。これは、私たちの腸管上皮細胞で作られ表層に分泌される粘液ムチンに微生物がビッシリと敷き詰められた様に存在し、外来からの有害菌を簡単には寄せ付けず、侵入を許さないためと考えられている。この場合は、腸内細菌は「味方」と化すのである。また、私たちが少々貧しい食事でもビタミン不足に陥らないのも、腸内微生物が各種のビタミン類を多量に生産して供給してくれるからである。この2面性を持つ大切な腸内細菌の中でも、良い菌の代表である乳酸菌が私の研究対象である。
私たちの腸内には、200種類以上の微生物(腸内細菌)が存在し、その細胞総数は実に100兆個も存在すると考えられている。この数は、私たちの体自体を構成する細胞の数(60兆個)よりも実に大きな数なのである!従って、腸内微生物は私たちの腸内の健康だけに留まらず、私たちの全身の健康を左右すると考えられている。その意味では、日頃全く見えないために考えたこともない腸内細菌は、実は私たちにとってとても重要な存在であり欠くことの出来ないパートナーなのである。
近代細菌学の黎明期の研究はルイ・パスツールにより開始され、寒天を入れた培地をシャーレ内で固める固形培地を開発したロベルト・コッホにより進められ、微生物を好気的または嫌気的に温度を一定にして培養することで飛躍的に発展した。この固形培地上に菌体が増殖した塊(コロニーという)が得られれば、大成功である。これを顕微鏡で覗けば、形態が丸い球菌なのか、細長い桿菌(かんきん)なのか、その中間なのか、ぱらぱらの単菌なのか、連なっている連鎖状菌なのか、その大きさはどの位なのかがすぐに判る。目に見える形で微生物が捉えられれば、研究の大半は終わったとも言える。純粋な菌体が培養で少しでも得られれば、遺伝子を取り出してその情報から、どの様な微生物に分類され、良い菌なのか、安全な菌なのか、病原性があるのか、遺伝子の数と種類、転写・翻訳される酵素などのタンパク質の数や種類や機能まで推定できる。しかし、自然界からこの様な培養でコロニーの得られる微生物はごく僅かであり、実際の検出率は1%以下と考えられる。すなわち、私たちは自然界の微生物の僅か1%以下しか見えていないのであり、99%以上はまだ私たちが出会ったことのない未知の微生物なのである!地球上に存在する数多くの現代でも原因不明の風土病や疾患や疾病の多くは、未知の微生物(細菌、酵母、カビやウィルス)が原因であると考えられている。
最近では、微生物の染色体DNAを取り出し、ゲノム情報を遺伝子解析するという分子生物学的アプローチが可能となった。この方法では、微生物を固形培地上にコロニーとして捉えなくても、DNAの配列情報によりその微生物の存在を確認することが出来るという画期的な手法である。しかし、このゲノム情報解析による分子生物学的アプローチでも、全ての微生物の生命現象の完全解明は難しい。一方、どんなに培地成分を改良して増殖促進因子などを加えても、培養の出来ない微生物(難培養性微生物という)が多数いることが、海水、糠床、ビールや腸内細菌叢で実際に確認されている。さらに、微生物のゲノム情報を丸ごと採取して理解しようと努めるメタゲノム解析でDNA情報は分析できても、全くその顔が見えてこない微生物が自然界にはまだ多いという事実の指摘は、私には本当に目から鱗であった。しかし、この「99%以上の菌を人類は研究対象としていない」という現実は、この学問領域への無限の興味と可能性を感じる。
「木を見て森を見ずの研究をするな」と、常日頃、恩師の伊藤敞敏先生から院生時代から助教授時代を通して教えて頂いた。私は現在、腸内細菌叢におけるプロバイオティック乳酸菌の有用性を、腸管付着活性という観点から研究している。プロバイオティクスは、Fullerにより提唱されたヒト腸管におり有益な保健効果をもたらす生きた微生物と定義される。私は、この腸内環境を一つの独立した生命体として微生物と宿主関係を考える視点を持ち、同時に地球微生物全体の一部として捉える網羅的な視点も忘れないようにしたい。
2004年、著名な科学誌であるScienceに、南米の血液型O型が多い国の胃がん患者から採取されたピロリ菌は、O型に特有の糖鎖構造(H抗原という)であるFucα1-2Gal-という構造を認識して付着するように進化しているという重要な報告がされた。すなわち、ある特定の胃腸疾患の中には、血液型を認識して付着増殖する有害菌が存在しているという新しい事実の指摘であった。私たちは、同じ血液型抗原を認識して結合する良い菌である血液型乳酸菌を、世界で初めて発見して報告した。大草敏史先生(慈恵医大)は、日本でも急増している潰瘍性大腸炎(UCともいう)の原因菌の一つにバリウム菌を想定されており、抗生物質によるピロリ菌の除去にヒントを得られたATM抗生剤療法が高い評価を受けている。私たちの研究は目に見えないが、例えばA型のヒトの腸管上皮へのA型病原菌による「感染」を、良い菌であるA型乳酸菌を用いて「競合阻害」、「排除」または「防御」するという作戦で、私たちの腸内の健康を守りたいと考えている(図参照)。

図 血液型乳酸菌による、同一レセプターをめぐる血液型病原菌の競合排除のメカニズム
①血液型抗原をレセプターとする病原微生物が腸管に付着する。
②血液型認識性乳酸菌が余っている血液型抗原に付着・増殖する。
③乳酸菌が産生する乳酸・酢酸・プロピオン酸やバクテリオシンのような抗菌物質の産生と、栄養物質の争奪により病原微生物が排除される。(過酸化水素、酸化還元電位の低下も抗菌的に働く)
④乳酸菌が定住化することにより同じレセプターを持つ病原微生物の付着・感染を阻害する。また、乳酸菌の持つ免疫賦活化作用により生体の免疫力を高める。
長沼毅先生(広島大)は、地球上生物を細胞数に換算すると、陸上・海洋の両方を合わせて1028個であるが、地下微生物は1030個と約100倍も多く存在すると指摘された。この試算は私には大きな衝撃であり、日頃の地球上での研究でもなお見えない部分が、自分の研究する研究室の地下にさらに存在したのかと、また見えない部分の存在と大きさに愕然としたものであった。陸上・海洋では2兆トンとバイオマス(生物量)は計算されるが、地下微生物では約3-5兆トンと圧倒的に地下の方が多いが、実は我々は全く見えていないのである。しかし、私たち個々人の腸内細菌のバイオマス量も、地上微生物全体のごくごく一部かもしれないが、宿主にとっては相当なウェイトを占めている。
思考や視点の辺境や極限にこそ「真実」の存在する可能性が高いと考えられている。そもそも、腸内微生物を善玉菌とか悪玉菌とか日和見菌と分類してレッテルを貼ることが、見えない部分をマスキングしているのかも知れない。これからは、見えない部分もしっかりと見ることにより、従来の考え方を越えた科学の醍醐味を、次代を担う若い研究者は微生物学の研究分野で是非堪能して貰いたいと考えている。
◆プロフィール◆
齋藤 忠夫(さいとう・ただお) (1952年生)
1975年東北大学農学部卒業。1981年福島学院大学・非常勤講師。1982年東北大学大学院農学研究科博士課程修了(農学博士)、東北福祉大学・助手。1987年米国ブランダイス大学・生化学部(博士研究員)。1989年東北福祉大学・講師。1989~1996年東北大学農学部・助教授。1997~2001年東北大学大学院農学研究科・助教授。2001年~東北大学大学院農学研究科・教授 現在に至る。
専門研究分野:畜産食品化学、応用微生物学、糖鎖生物工学
受賞:日本酪農科学会賞(1998)「牛乳の糖質および糖タンパク質糖鎖に関する研究」。日本畜産学会賞(2002)「プロバイオティック乳酸菌の有効利用に関する研究」。
業績:原著論文180報。総説60報。
著書には、「最新畜産物利用学」「最新畜産学」「畜産食品の辞典」「酵素ハンドブック」(朝倉書店)、「動物資源利用学」(文永堂出版)、「ミルクの先端機能」(弘学出版)、「食料の百科事典」(丸善)、「発酵乳の科陰学」(アイ・ケイコーポレーション)、「農学大事典」(養賢堂)など30冊。
学会活動:日本乳酸菌学会理事(大会担当)、日本酪農科学会常任幹事・編集幹事、日本農芸化学会代議員・学術活動強化委員・常任論文審査委員、日本食品免疫学会評議員、日本農芸化学会東北支部会評議員、日本生物工学会北日本支部評議員、東北畜産学会評議員、(財)日本乳業技術協会評議員、(財)糧食研究会評議員など。
研究室ホームページ:http:/www.agri.tohoku.ac.jp/douka/index-j.html
(CANDANA235号より)