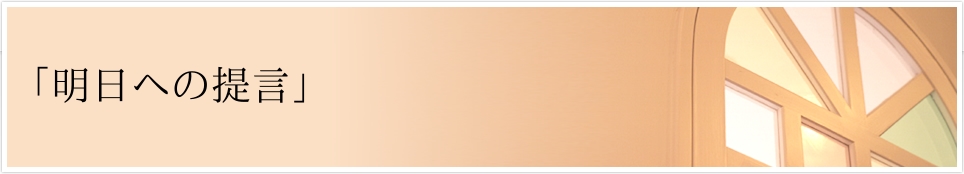速水 侑(東海大学名誉教授)
平泉の世界文化漬産誉録再トライ
昨年12月12日付『朝日新聞』は、文化庁が、奥州藤原三代によって築かれた平泉を「平泉一仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群」として世界遺産条約の文化遺産に推薦することを決めたと報じた。平泉は2008年にも登録申請したが、ユネスコの世界遺産委員会で登録延期と判断されていた。文化庁では今年1月に推薦書を世界遺産センターに提出し、2011年の登録を目指すという。また、再トライする今回の登録予定の文化遺産は前回の申請と異なり、中尊寺など浄土思想関連のものに絞り込む形になるようである。昨年来、私は平泉と天台浄土教の問題について幾度か触れることがあったが、ここでは世界文化遺産としての平泉の今日的意味を中心に述べてみたいと思う。
東北地方と天台浄土教
奥州藤原氏の初代藤原清衡(1056~1128)によって建立された関山中尊寺の現在の寺格は天台宗東北総本山である。天台尼瀬戸内寂聴の出家の場としても知られるが、天治3年(1126)の落慶供養法会に唱導(導師)として延暦寺から相仁已講が招かれたことでも明らかなように、もともと天台宗の寺院として創建されたのであり、二代基衡の毛越寺、三代秀衡の無量光院も同様である。なぜ平安末期の12世紀に、東北の支配者奥州藤原三代は天台宗、別けても天台浄土教に帰依したのであろうか。
東北地方の仏教は、円仁(794~864)の布教を契機として、9世紀以降天台宗が主流を占めるようになった。円仁は下野国の豪族の家に生まれたが仏門に入り、地域民衆に菩薩と尊敬された広智に伴われ比叡山に登り最澄の弟子となった。最澄の東国布教に随行したが、さらに最澄没後には陸奥・出羽にも布教したらしく、13世紀中頃の『私聚百因縁集』が「化道は遥に東夷の栖を過ぎ、利生は遠く北狄の境に及ぶ。いわゆる出羽の立石寺、奥州の松嶋寺などなり」と讃えたように、立石寺はじめ東北の寺々には、多くの円仁伝説が語り継がれている。円仁を仏道に向わせた契機は、中央政権の蝦夷征服戦争によって重い負担を課され疲弊した東国民衆の姿であったろうといわれるが、政治的にも社会的にも不安定な東北の地に「鎮護国家」と「福利人民」の天台仏教を顕現することで民衆を救済しようとする円仁の遺志は、天台浄土教を統一理念の核として戦乱なき支配圏の確立をめざした奥州藤原氏に受け継がれていったと見ることもできるであろう。
東北布教後の円仁は、入唐求法して天台宗を興隆し第三世天台座主となり、慈覚大師の号を贈られた。彼は入唐求法によって天台密教の充実を図り、顕密兼修は天台宗の通例となった。また常行三昧の作法として導入した五会念仏は山の念仏と呼ばれ、心身の罪咎を消去する阿弥陀念仏として発達し、天台宗は浄土教の主流となった。ことに源信の『往生要集』によって天台浄土教が確立すると、11世紀以後の京都の貴族社会では、藤原道長の法成寺阿弥陀堂や藤原頼通の宇治平等院鳳凰堂など、極楽浄土の様を彷彿させる阿弥陀堂の造営が盛んになり、念仏往生者の行実を記録した往生伝も多数編纂された。
こうした天台浄土教は、どのようにして京都の貴族社会から東北地方に広まったのであろうか。『続本朝往生伝』は、陸奥守藤原基家(1093年没)の母や陸奥守源頼俊(1070年当時在任)の娘など、京都から赴任した陸奥国守の家族に熱心な念仏往生者がいたことを伝えている。また、立石寺入定窟の円仁遺骨収納とされる金棺は中尊寺金色堂の金棺と類似し、天台浄土教流布により円仁を往生者と見なす11世紀後半の作とする説もあり、藤原清衡当時、天台浄土教が東北の地に広まっていたことは疑いない。
清衡の身辺に道俊という熱心な念仏者がいたことも『三外往生記』は伝えている。道俊は京都の人であったが陸奥国に赴き、文筆を以て清衡に仕え恩顧を受けた。極楽往生を願い、朝夕に弥陀仏を念じ観音経を誦し、79歳になった1131年、独り持仏堂に入り、西に向い念仏して眠るように入滅したという。それは清衡没後3年に当たり、晩年の清衡は同世代の道俊の念仏信仰を間近に見ていたであろう。しかし私は、清衡が天台浄土教に帰依した原点は、前半生の過酷な戦乱の自己体験にこそ求められるべきだと思う。
藤原清衡と天台浄土教
清衡は、『中尊寺供養願文』で自らを「東夷の遠酋」と記すように、陸奥国の俘囚長である安倍頼時の娘を母として生まれた。幼少期の円仁が心を痛めたであろう蝦夷征服戦争で征服された蝦夷の多くは俘囚集団として北辺の城柵などに配置され、その中で人望あるものが長として国司の監督下に置かれたが、俘囚長の安倍氏は勢力を拡大し国司に服さぬ地域支配を実現した。中央政府は討伐のため源氏の棟梁源頼義を陸奥守に任じ、頼義は苦戦の末、出羽国の俘囚長清原武則の援軍を得て、1062年に安倍一族を減した。いわゆる前九年の役である。清衡の父藤原経清は刑死したが、7歳の清衡は父の敵の武則の子武貞に母が再婚したことで命を長らえた。しかし武貞には先妻の子真衡がおり、再婚した母は家衡を生んだから、連れ子の清衡にとって忍従の日々であったろう。武貞没後、後三年の役と呼ばれる3兄弟間の争いが起り、清衡は弟家衡によって妻子を殺されるという悲劇を乗り越え、1087年、安倍・清原両氏の遣領を継承し全奥州の支配者となった。
奥州全土を巻き込んだ過酷な戦乱は、勝者にも深い心の傷を残した。『続本朝往生伝』などによると、安倍氏を減した源頼義は、征夷の任にあたって殺生の罪を重ねたことを深く悔い、阿弥陀堂を建てて念仏し遂に出家した。堂の下には、多年切り集めた戦没者の片耳を埋めて供養したという。父を殺され兄弟相食む戦争の残酷さを体験した清衡も、阿弥陀の救いを求めた。しかし安倍・清原両氏の継承者として一人生き残り、奥州の専制支配者となった彼は、頼義と異なり、為政者の立場から鎮護国家と福利人民を説く天台の教えを統一理念として、まず戦乱なき「現世の浄土」を奥州に実現しようとしたのである。
『吾妻鏡』に収める中尊寺僧の注申文や『中尊寺供養願文』によると、清衡は奥州支配の最初に、安倍氏の故地衣川関近くの平泉に中尊寺を創建した。そして南端の白河関から北端の外ヶ浜まで支配圏を貫く街道の一町ごとに金色阿弥陀笠卒都婆を立て、中心にあたる中尊寺を旅人往還の通路として奥州統一の理念を示すとともに、三丈金色阿弥陀巨像の周囲に丈六九体阿弥陀像を配置する大長寿院を建てて、上品上から下品下まですべての人々を極楽に救済しようとする支配者の慈悲を示し、金色堂に阿弥陀像と六地蔵を安置し、六道輪廻の衆生も極楽に導こうとした。さらに巨大な鐘楼を建て、地の果てまで響く鐘声によって、山野に迷う奥州多年の戦乱犠牲者の怨魂を官軍賊軍の区別なく浄土へ導くよう願ったのは、戦乱を体験した彼の信仰の原点を示している。中尊寺供養を終えた清衡は、「入滅の年に臨んで俄に始めて逆善を修」し、合掌して仏号を唱え閉眼したという。
平泉文化の今日的意味
清衡は『供養願文』で「中尊寺は王化の及ぱぬ蛮地だが、界内の仏土というべきであろう」と、中尊寺こそ中央の支配が及ばぬ辺境に実現した「現世の浄土」であることを誇示した。続けて清衡は、自分が祖先の余業を受け俘囚の頭となって30余年、陸奥・出羽の地に征討の戦は無く天下太平を享受できたと聖代の仁恩を讃えるとともに、貢納の勤めを永年怠り無く続けたことを強調している。現世の浄土は平和な社会によって実現される。清衡は、京都の中央政権に貢納協調することで軍事介入の口実を与えず、永く戦乱に苦しめられていた東北の地に初めて平和な社会を実現したのである。基衡・秀衡も清衡の政策を忠実に継承して源平の争いにも局外中立の態度を持し、戦乱の時代に100年に及ぶ平和と京都を凌ぐ仏教文化都市平泉を現出した。平和憲法を理念とする戦後の平和が未だ60余年に過ぎないことを思えば、それは驚くべき長さである。しかし、源頼朝が東国に軍事政権を樹立して平泉と中央政権の紐帯を遮断した時、清衡以来の貢納協調政策は破綻した。1189年、奥州藤原氏は滅亡し、その版図は鎌倉御家人たちに分割されてしまった。
天台浄土教を理念として戦乱なき現世の浄土を実現しようとする清衡の願いは100年後に挫折したが、二度の悲惨な世界大戦を経験しながら未だ戦火の絶えない現代において、平泉の歴史は極めて今日的な問題を提起している。人類が求めて止まぬ平和な社会は、果して現世に実現できるのか。軍事的暴力の前に宗教的平和の理念は無力なのか。世界文化遺産を目指す平泉は、その金色の輝きの内に、重い問い掛けを今も続けているのである。
◆プロフィール◆
速水 侑(はやみ・たすく) (1936年生)
北海道に生まれる。北海道大学大学院文学研究科博士課程単位取得。北海道大学助手を経て東海大学教授、東海大学文学部長、文学研究科委員長、附属図書館長。現在、東海大学名誉教授。
著書に『観音信仰』(塙書房1970年)『弥勅信仰一もう一つの浄土信仰一」(評論社1971年)『地蔵信仰』(塙書房1975年)『浄土信仰論』(雄山閣出版1978年)『菩薩一仏教学入門一』(東京美術1982年)『平安貴族社会と仏教』(吉川弘文館1983年)『日本仏教史古代』(吉川弘文館1986年)『呪術宗教の世界一密教修法の歴史一』(塙書房1987年)『源信』(吉川弘文館1988年)『観音・地蔵・不動』(講談社1996年)『地獄と極楽一往生要集と貴族社会一』(吉川弘文館1998年)『平安仏教と末法思想』(吉川弘文館2006年)などがある。
(CANDANA241号より)