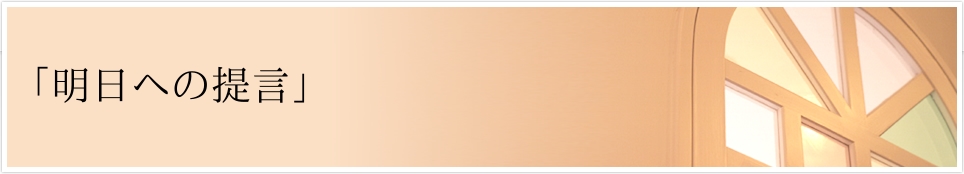小栗純子(中央学術研究所講師)
焦燥感にかられて
新しい時代の流れについていけない、焦りと苛立ちを感じたことはないだろうか。
私はことし65歳になるが、昭和から平成へと変わった頃から、変貌する時代の流れと自分の中のずれを、少しずつ感じるようになっていた。それから何年かすると、徐々に進んでいたIT化と国際化の流れに、私はすっかり取り残されていた。
そのころ私は50歳であったが、親の介護や経済的な諸問題を抱え、毎日の仕事をこなすだけでいっぱいだった。ようやく生活が落ち着いたころには、還暦をすぎていた。時代は21世紀に入り、2006年になっていた。まずパソコンの使い方をきちんと学ぼうと考えた。この歳になって人に何か習うには勇気がいる。教える立場に長くいると、教えを受ける側にまわるのはかなり抵抗がある。ある日、思い切って地元の商店街のパソコン教室に飛びこんだ。そのころの私は、パソコンは原稿を書くだけのもので、ほとんど使い道を知らなかった。半年ほど週3日、ノートパソコンを持ちこんで教室に通い、色々な機能を学んだ。新しいことを学ぶのは、新鮮ではあった。しかし学んだことを、自分の暮らしや仕事にどのように取り入れたらよいかまだ分らなかった。
ニュージーランドの旅
その年の秋、大学時代の友人洋子さんがニュージーランドから電話をくれた。洋子さんは、現地の小学校で、ボランティアで日本の文化を紹介する仕事をしていた。日本では約40年小学校の教師をし、10年近く校長を経験して定年を迎えていた。彼女がニュージーランドの北島にあるタウランガヘ行くと聞いたとき、正直かなり驚いた。洋子さんは英語を話せなかったからである。「何とかなるわ、英語はともかく子供に教える技術はあるから、心配ないわ」と、元気に旅立ったのだった。勇気があると感心したが、少し無謀にも思えた。どうなるのかな、その後も心にかかっていた。3ヶ月ほどして、便りがあった。美しいコバルトブルーの海岸の写真ハガキには、現地の小学校で働く彼女の毎日が生き生きとつづられていた。心配はどこかに消え、羨ましい気持ちと、自分だけが古い時代に取り残されてしまったような、淋しい気持ちになった。
それからしばらくして、思いもかけない洋子さんからの電話であった。「こちらに来ないか」という誘いであった。「来るならM夫人を連れてきてほしい」という。行きます、いい機会だもの、私は二つ返事で承諾した。
ニュージーランドへの旅は、久しく感じたことのないわくわく感を伴う旅であった。洋子さんがどんな暮らしをしているのか、興味があった。最大の関心は、彼女の英語がどうなったか?であった。私がM夫人と、成田からオークランド行きの飛行機に乗ったのは9月半ばであった。現地は南半球だから、季節は春であった。オークランドは人口約100万、ニュージーランド最大の都市、経済の中心地である。タウランガはここから東南約200キロにある、人口10万のリゾート地だ。小型飛行機に乗り換え、20分で到着した。私達2人は洋子さんのホームステイ先、スミス夫妻の家に向かった。その日、洋子さんは久しぶりに、日本語が話せたので嬉しくて興奮気味で、女3人のお喋りは夜中まで続いた。洋子さんはみごとに英語を使いこなしていた。彼女の語るところによれば、はじめの1か月は、英語が聞き取れず、大変な苦労をした。職場で英語が分らなければ仕事にならない、必死になって耳を集中させ、その日一日の仕事をこなすのがやっとだった。帰宅した後は疲れ果て、夕食後は部屋にこもり、毎晩3時間以上も辞書と首っ引きだった。辞書を引く回数が減ったなと感じたのは3か月くらいたってからだった。
2週間の滞在であったが私たちはスミス夫妻と5人で、一泊のドライブ旅行、浜辺のハイキング、買い物も楽しんだ。また、私たち3人は、少しお金を張り込んで、ヘリコプターでタウランガの町を上空から見物した。美しい海と、どこまでも続く広大なキーウイ畑の中に家が点在していた。スミス夫妻の家は日本風に言うと2000坪の敷地に、寝室3部屋、ダイニングキッチン、12畳ほどのリビング、20畳くらいの娯楽室があった。家の中はきれいに整理整頓され、清潔感にあふれていた。庭の半分は果樹園で、オレンジの樹がたくさんあった。たわわに実のついたオレンジを私たちは自由にもぎとり、思う存分に食べた。子供の頃に帰ったようだった。私はM夫人と同室であった。
M夫人は学校で、英会話を習っていた。一緒に寝泊りするうちに、彼女が通っている学校の様子を何度も聞くことができた。オーナーは30代はじめのアメリカ人で、スタートして2年足らず、新宿にあり、英会話とフランス語会話の個人授業だけの小さな学校である。
英語はいまや世界共通語であるから、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、マレーシアなど、色々な国の英語にふれることが大切だというのが学校の方針。授業は先生と生徒がマンツーマン方式で、1回のレッスンは40分、すべて英語で行う。またIT化した英語の教育で、学校のコンピューターと生徒のパソコンは繋がっている。レッスンは毎回録音されていて、自分のパソコンにダウンロードすれば、いつでも聞くことができる。話を聞くたびに、ここまで進化しているのかと驚いたが、パソコンを勉強したお陰で、M夫人の話はかなり理解することができた。
この旅の一番の収穫は私も英語を話せるようになりたいと奮起したことであった。洋子さんが、60からでも遅くはないことを証明してくれた。それと、自分の英語がどうにもならないことも悟った。「日本へ帰ったら英語を始めるぞ、今が最後のチャンスだ」と思うにいたった。
新たなる出発
帰国して3日後、私はM夫人の案内で始めて学校を見学した。できたばかりの学校は若くてフレンドリーな外国人の先生とスタッフたちで、活気にみなぎっていた。学校の小さなロビーで、お茶を飲みながら先生と生徒たちが自由にお喋りをし、英語とフランス語が飛び交っていた。“新宿の中に外国がある”と私は思った。また、最先端のIT化した設備と、学校のオーナーのポジティブな発想はこれからの発展を予感させた。私はここに入学を決め、つぎの日から学校に通いつづけた。1年目は英語だけだったが、2年目からフランス語もはじめた。気持ちも若返り、学生時代に戻ったようだった。
英語は3か月くらいで、簡単な会話ができるようになり、1年もすると日常会話には困らなくなった。フランス語は、アルファベットも知らずに始めたので、かなり苦戦した。その後、縁あって自宅の別棟に2人のフランス人の先生が越してきてから、実践で使う機会が増えた。時々パーティーにも呼んでくれるので、フランスだけでなく、ヨーロッパの色々な国の人と話す機会に恵まれるようになった。パーティーの常連たちを、今年の正月に私の家に招き、おせち料理とお雑煮をご馳走した。平均年齢27,8歳という若い世代、それも国籍も人種も違う人達と友達感覚でつき合っている。少し前までの私なら考えられないことである。彼らとの電話、メールでの連絡は英語、フランス語、もちろん日本語も使っている。でも私の英語とフランス語は人さまに聞かせるほど上手くない。しかしコミュニケーションは十分成り立っている。人と比べて上手い、下手は問題ではない。流暢に話す人を見て、恥ずかしいと思ったりめげる必要はないのだ。ただ昨日の自分より、今日の自分がほんの少しだけ上達していればよいのだ。あくまでも自分の英語、自分のフランス語でよいと、開き直っている。
海外旅行もそれまでとは一味違うものになってきた。外国人と言葉を交わし、少しでも異文化にふれることは、刺激的で楽しいことである。つい最近、パリの街を一人で観光した。フランス語で買い物をしていたら、日本人観光客に「パリに住んでいるんですか?」と聞かれ、おもわずにんまりしてしまった。
気がつけば、心の奥底に抱えていた焦りや苛立ちは、いつのまにか消えていた。人生100年の時代だ。まだ、30年は生きると思っている。これからさらに、IT、国際化は、地球的規模で進んでいく。私はまだ65歳、私の進化はいま始まったばかりである。
◆プロフィール◆
小栗純子(おぐり・じゅんこ) (1945年生)
新潟市に生まれる。法政大学文学部史学科卒。日本宗教史専攻。立教大文学部講師、放送大学客員助教授などを経て、現在中央学術研究所講師法政大学講師(非常勤)。
著書 『日本の近代社会と天理教』(評論社1969年)
『天理教一中山みき』(新人物往来社1970年)
『妙好人とかくれ念仏』(講談社1975年)
『女人往生一日本史にみる女の救い』(人文書院1987年)
共著 『教祖誕生一親驚と中山みきにみる』(日本経済新聞社1968年)
『人間の歴史一宗教にみる日本女性史』(放送大学教育振興会1986年)
『日本仏教史』(法政大学通信教育部1990年)
2001~2008年の7年間、東京女子大学名誉教授大隅和雄氏と共に開祖顕彰事業聴取り調査に携わる。
(CANDANA242号より)