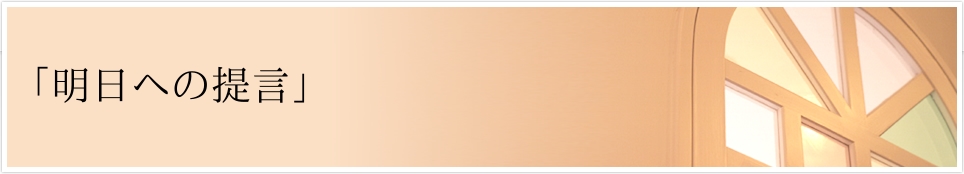竹村 牧男(東洋大学学長)
1.明治初期の日本仏教界の状況
日本の仏教諸宗は、江戸時代、幕府による本末制度の強化により、自由な布教に制約を受け、かつ寺請制度(檀家制度)の推進により、布教活動への活力を失っていった。さらに幕末から明治にかけて、廃仏毀釈の運動が各地で起こり、その運動は特に明治当初の「神仏判然の令」によってより一層はげしくなり、仏教界の打撃は大きかった。
さらに西欧各国の来襲とともに明治政府は極端な欧化政策を推進したことから、伝統的な仏教思想は省みられなくなり、仏教界は沈滞への一途を辿ることになる。日本では、豊臣秀吉のバテレン追放令(1587)以来、江戸時代を通じてもキリスト教禁止政策が一貫して取られ、明治新政府もこの姿勢を引き継いでいったが、しかし諸外国の圧力に抗することができず、明治6年(1873)にはこの立場を降ろさざるをえなくなり、その後はなし崩し的にキリスト教の伝道が普及し、旧態依然の仏教界はそうした時代の中で息をひそめるだけであった。
その明治初期の時代に少年時代を送った円了は、寺院の出身であるにもかかわらず当初、仏教に対して懐疑的ですらあった。むしろ「これを非真理なりと信じ、誹謗排斥する事、亳も常人の見るところに異ならず」(『仏教活論序論』)というありさまであった。
2.円了における哲学と仏教
しかし円了はやがて東京大学で西洋哲学を学び、ヘーゲルの思想を高く評価するとともにその立場から仏教を見直して、仏教思想の優れた点を改めて深く認識することになる。ではいったい、円了は西洋哲学のどこに真理を見出したのであろうか。円了は主としてドイツ哲学に深い関心を寄せ、カント・フィヒテ・シェリング・ヘーゲルとドイツ哲学が深まっていく様子を描写しつつ、最終的に次のように判断している。
「故にヘーゲル氏は相対の外に絶対を立てずして、相対の体すなわち絶対なりとす。他語をもってこれをいえば、氏の説、相対と絶対とは全く相離れたるものにあらずして、互いに相結合して存し、絶対の範囲中に相対のあるゆえんを論定して、相対中にありてよく絶対のいかんを知り得べきものと立つるなり。この絶対の全体を理想と名付け、その体中含有するところの物心両界を開発するもの、これを理想の進化という。……ドイツ哲学ここに至りて始めて大成すというべし。」(『哲学要領』(前編))
このように、いわば相対即絶対・絶対即相対の思想に、ドイツ哲学の最高峰を見たのである。と同時に円了は、その最高峰の思想が、実は天台の真如縁起説や華厳の法界縁起説と同等のものであることを見きわめ、仏教は西洋哲学に勝るとも劣らない思想を有する貴重なものであると領納したのであった。
3.円了の仏教復興運動
円了はこの立場から、俄然、仏教の擁護に努めていく。まずは、キリスト教の虚妄性を論じ、一方、仏教は思想的にきわめて優れたものであることを論じた。『真理金針』や『仏教活論』等はその論陣である。これらの書物によって、「仏教徒は初めて自家の宝蔵に気づき、大いに活気を呈した」(平野威馬雄『伝円了』)のである。
ところで、明治19年(1886)ころから、諸外国との間で、「外国人の内地居住・動産不動産等の権利を日本国民と同等にすること」が大きな問題となってきた。円了は、明治21年の海外視察より帰国後の頃には、故郷の実家の寺に一度は帰省するようにと促す父に対して、今、いかに仏教が危機的状況にあるかをるる説明する手紙を書いている。すなわち、明治22年の憲法の発布によりキリスト教の伝道は自由となったこと、社寺局は廃止・寺院の墓地取払い・寺院の境内地取上げ・本山管長の廃止・住職僧侶の名義の廃止は間近であること、内地雑居の公許によりキリスト教は大勢力を得、仏教は廃滅に至るであろうこと、国会に宣教師は出席権を有するも僧侶は出席できないこと等をあげ、自分はその状況に対し、仏教の復興に全霊をかけるということを、父親に対して切々と書くのである。
「今や日本全国の仏灯まさに滅せんとするの時なり。今や仏教総体のために生死を決せざるをえざる危急存亡の秋なり。……私儀はこの仏教総体の存廃に付き、多年苦心罷り在り、今九死一生の危急に相い廻り候らえば、必死の勢いにして、せめて来年国会前に何とか仏教護持の一方相立てたく、一人にてその途に当たり、昼夜心痛これ有り候。……」(明治22年8月28日付井上円悟宛書簡)
続いて、政府へ建白書を出す決意を語り、狂人とのそしりを厭わないと訴えている。この間のことについて平野威馬雄は、「仏教公認運動のリーダーとなって陣頭に立った円了は、その年の秋には京都の各宗本山を歴訪し、各宗本山では団結してその実現に協力することに同意した。つまり、『仏教を公認せよ』という建白書を内務省に提出しようという議なのである。帰京後ふたたび東京の各宗寺院をまわって諒解を得、各宗連合を結成した。そこで愛宕下・青松寺に各宗の管長と会合し、いよいよ本格的な運動を展開することになった」等と説明している(『伝円了』)。
こうして、円了の懸命な活動によって、瀕死の状況にあった仏教界は息を吹き返し、活気を帯びて来るのであった。この結果、「日本人の海外発展にともなって、朝鮮、中国大陸、ハワイ、北米に布教線をひらこうとする新路線を見出した」のでもあった(同前)。
4.円了の仏教改革への視点
また、円了は仏教界に対して、各宗ともに根本からその教義を建て直し、かつ厭世教の評判をくつがえして、現実社会を指導できるよう改良すべきであると訴えるのであった。たとえば、仏教は往々、死後の冥土のことのみを説き、出世間的出離解脱の一道のみを説いて世間道を説かないが故に、世間は仏教を厭世教と誤解している。重要なことは、今日以後は世間道を表にし、出世間道を裏にし、二者の両全を本として、仏教の弘通に力を尽くすことだと強調する(「内地雑居に対する教育家、宗教家および実業家の覚悟」)。円了は、仏教そのものを世間を益するものに変えなければいけない、それが仏教改革の根本問題であるとするのである。
明治25年1月、東京・京都の学生を中心として大日本仏教青年会が設立されたが、このいつの時かの講習会に円了が招かれたのであろう、そこで次のように説いている。
「そもそも大聖釈迦牟尼仏は、ひとたび摩耶夫人の体内に宿りしより、沙羅双樹の間に円寂を示せしまではもちろん、その遺教の今日に伝わりて、四億五億の生霊が随喜追慕してやまざるありさまを考うるに、宇宙の一大精神が発動開現して、この大覚者を降誕せしめたるやの感なきにあらず。ゆえに、余は釈迦仏の本地は決して三千年古の悉多太子にあらずして、久遠劫来の覚者、無始以来の仏なるを信ず。……これ(釈尊の一生)、あに宇宙の大勢力の活動発現にあらずしてなんぞや。……換言すれば、無始以来この大宇宙が懐抱しきたれる至高至大の精神が、忽然として釈迦牟尼の心底をわき出でたるものなるを信ず。」(「仏教改革私見」)
このように、釈尊の根本に無二の大願と無限の大悲、至高・至大の精神が存在しているのだとし、今日の仏教はどの宗派であれ、それこそを具現すべきことを訴えるのである。
さらに、円了は浄土真宗の寺院の出身であったが、死後の浄土往生を望むのみの仏教より、この地上の社会の改革に取り組もうとする日蓮宗を高く評価するほどであった。このことについては、次のように説いている。
「余案ずるに、日蓮宗の長所は、現世を本とし世間を目的とするにあり。……今後の仏教は世間門を先として出世間門を後にし、俗諦門を表にして真諦門を裏にせざるべからず。日蓮宗のごときは、すでに厭世教にあらずして世間教なれば、この際さらに進みて国際の競争に加わり、あくまで国家を円満ならしむることを目的とすべし。他の宗派も、永くこの国に栄えんと欲せば、必ずこの方針を取らざるべからず。しからずんば、僧侶は世間の廃物視せられ、寺院は無用視せらるるに至るは必然の勢いなり。しかりしこうして、余は日蓮宗に向かいて、今後の仏教改良の先鞭をつけられんことを望む。その方針たるや、世間的、競争的、有為的、進取的ならざるべからず。かくして、仏教は厭世教なり、僧侶は墓番なり、寺院は葬式取扱所なりとの妄評を説破せざるべからず。」(「将来の仏教につきて日蓮宗諸師に望む」)
なお、日蓮宗に対しては、「爾後、日蓮宗と他宗との間は、開港通商的精神を持って相交わり、互いに彼が長を取りて己の短を補い、もって宗派の統一と教理の円満を祈らざるべからず」と述べ、その排他的性格を克服するよう、訴えている。
まとめ
円了の立場は、時代の制約もあって、確かに国家主義的な面が否定出来ない。その背景には、当時の全体的な社会の事情もあった。もちろん今ではその正当性も厳しく吟味しなければならないが、しかし円了が当時において力説した、「仏教は現実社会に深く関わるべきだ」「仏教は世間的、競争的、有為的、進取的になるべきだ」とする主張は、今日の日本仏教にとってなお重要な課題であろう。アメリカでは、Engaged Buddhism といって、社会的実践を尊ぶ仏教が盛んとなり、それが日本にも入ってきているが、それがどこまで日本仏教の改革に影響力を及ぼせるかは、今後の仏教復権への鍵となることであろう。ともあれ、仏教の哲学を深く究明し、その立場から現実社会の改革に参画する仏教を構想した円了の志を、日本の仏教界は今後もよく考えていくべきだと思われるのである。(了)
◆プロフィール◆
竹村 牧男(たけむら・まきお) (1948年生)
東京生まれ。1971年東京大学文学部卒業。1974年東京大学大学院印度哲学博士課程中退。文化庁宗務課専門職員、三重大学助教授、筑波大学助教授、同教授を経て、2002年より東洋大学文学部インド哲学科教授。2009年9月より東洋大学学長、現在に至る。研究分野:仏教学・宗教哲学。唯識思想研究で博士(文学)。主な著書として、『入門 哲学としての仏教』(講談社現代新書)2009、『〈宗教〉の核心――西田幾多郎と鈴木大拙に学ぶ』(春秋社)2012、『大乗仏教のこころ』(大東出版社)2013、『禅の思想を知る事典』(東京堂出版)2014、『日本仏教 思想のあゆみ』(講談社学術文庫)2015、その他、多数。
(CANDANA263号より)